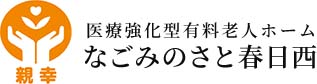2025.5.10
「博多南駅」
1990年4月1日、JR九州博多南線「博多南駅」(春日市上白水8丁目)が開設。当駅発着の列車(新幹線)は在来線特急扱いで、現在博多駅まで片道330円で乗車できます。2000年5月、丁度今頃に一度利用したことがありますが、通勤、通学、買い物など新幹線の乗客と違った人々が利用されていました。乗車客も少なく、充分に広い席に座って恋人同士とみられる若い男女が談笑していました。二人には、こんな人間模様があったかも知れません。

「博多南駅」
脇山博司
「ーーーじゃあさ、賭けをしようよ」
二泊三日京都旅行最終日の夕刻、乗り込んだ博多南行きの新幹線が動き出すと、わたしは隣の席で居心地悪そうに携帯電話をいじる恋人の広紀にそう告げた。散々な旅行だった。
何もかも任せると言いきった広紀に代わってわたしが、博多駅を発つ頃から綿密に組み立てたプランを、彼はことごとく無視して気ままに振る舞った。
初日、三十三間堂で自分と似た顔の千手観音を探し始めた彼に付き合って、銀閣寺の閉門に間に合わず。二日目の嵐山では、渡月橋からいきなり桂川の上流を目指してずんずん歩き出した。彼を追ったせいで、龍安寺の高名な石庭を拝めずじまいとなってしまった。
とうとう昨晩、食事の途中でケンカになった。

予定を狂わせたことを責めると広紀は、
「いいじゃんか。清子だって、俺にそっくりな像を見つけたときも、上流の方でもっときれいな紅葉を見られた時も、すっげぇはしゃいでたくせに」
開き直るのも腹がたつし、彼の言うとおりなのはいっそう腹が立つのだ。
結局わたし達は仲違いしたまま、最終日の今日は、すでに指定席を抑えてあった帰りの新幹線に乗るまで、完全に別行動となった。
合流しても二人の溝は埋まらず、しびれを切らしたわたしはついに、持ちかけたのだ。
ーーー賭けをしよう、と。
「賭けって、どんな」
心当たりがないはずもないのに、広紀は怯えるように頭を上げて問いただす。
「わたしたちが新幹線を降りるまでに、この客席に入ってくる人が一人でもいたら、わたし達は別れる。誰も入ってこなければ、別れない。それでどう」

百パーセントとまでは言わない。 が、こんな賭け、やるまでもなく結果は見え透いていた。それこそ終着駅を目指す新幹線のような、行き着く先の判りきった賭け。
それでもわたしは、確かめたかったのだ。 二人の旅の終着に、彼が何を望んでいるのかを。 広紀は少したじろいて、しかし深く悩むこともなく、答えた。
「いいよ」
新幹線が加速する。 わたしは背もたれに頭をあずけ、客室の前方に設けられた自動ドアを、祈るような思いで見つめた。
「じゃあさ、賭けをしようよ」
あれは二年前。 ひょんなことで知り合ってからというもの、しつこく誘ってくる広紀に根負けして、初めて二人で会った日の帰りのことであった。
彼と過ごした時間は楽しかった。 彼のことを、少なからず魅力的だとも思った。 しかしその一方でわたしは、この人とはとことん気が合わないな、とも感じていた。
何しろ彼は社交的で行動派、対するわたしは引っ込み思案。 アウトドアでスポーツを好む彼と、屋内で読書を愛するわたしとではとうてい、相性がいいとは思えない。

恋愛だって、どういうわけかこんなわたしにも積極的にアプローチしてくれる彼に対し、わたしはしぶりにしぶってようやく、デートぐらいならという気になった。
なのに彼はもう、付き合ってくれなどと言い出すのだ。 どちらかと言えば、断る方に傾いていた。
せめてもう少し様子を見たかった。 けれどもはっきり答えを出せずにいるわたしに、広紀が告げたのが先の台詞。
「俺は大橋駅で降りるから、それまでにこの車両に入ってくる人が一人でもいたら、俺と付き合ってよ。誰も入ってこなければ、今日のところは潔くあきらめる」
「意味わかんない。どうしてそんなことで決められなくちゃいけないの」
「清子ちゃんが自分で決められないなら、他の人に決めてもらうしかないだろ」
憮然としつつもわたしは考える。 二人を乗せた電車はそのとき、高宮駅に停車していて、ちょうどホームに面した扉が閉まったところだった。 次の大橋駅まではたったの二分、隣の車両から乗客が移ってくる可能性はゼロではないが、きわめて低いと思われる。
つまり、ここはひとまずあきらめてもらうことができ、彼との交際については結論を急がずに済む。

「いいよ」
わたしはうなずいた。
同時に電車が高宮駅のホームを離れ、大橋駅へと向かう、そう混み合ってもいない車内に人の動きはほとんど見られず、程なく電車は減速し、わたしが賭けに勝ったことを確信し始めたときだった。
広紀が突然、わたしのそばを離れて歩き出したのだ。 初め、降車に備え、乗車口の前まで移動しているのかと思った。 ところが彼はそこで立ち止まらず、なおも歩みを進める。
その先にあるものを見てわたしは、嫌な予感に顔をしかめた。 予感は的中した。 広紀はいったん隣の車両に移ると、すぐさまきびすを返し、また元の車両へ入ってきた。 そして、わたしに言ってのけたのだ。
「それじゃ、今日から恋人ってことでよろしく。清子ちゃん」
折しも電車は大橋駅に到着し、開いた扉から広紀は出ていった。 あまりにも馬鹿馬鹿しい決着にわたしは、電車が動き出したのちも固まってきり動けず、気がついたら自宅の最寄り駅雑餉隈駅を三つも通過していた。

「ーーー呆れてものも言えないってのは、まさにああいう心境をさすんだろうね」
新幹線が出発してから、五分が経過しようとしていた。
わたしが非難めかしく言うと、広紀は肩をすくめる。
「いいじゃんか。断ろうと思えば断れたはずだろ、そんなズルはなしだって」
「だね。あのときは何だか、もういいやって気分になっちゃった」
賭けの結果を受け入れたことが、よかったのかどうかはわからない。 けれどもわたしは、その判断を悔いたことはない。 まして人のせいにするつもりはない。

ふぅ、と息を吐き出すと、わたしはあまり間を置かずに続ける。
「いいんだよ、こんな賭け、さっさと終わらせてしまっても。そんなズルはなしだって、そんなこと、わたしは絶対に言わないから」
広紀は何も答えなかった。 わたしは腕時計を一瞥し、再び、自動ドアに視線を戻す。
二人の賭けは、まだ終わらない。 付き合う前の懸念は正しかった。
らとにかく二人は気が合わないのだ。 休日くらい外へ行こうと彼は言い、休日くらい家で休ませてとわたしは答える。 何が伝えたいのかわからない自己陶酔みたいな歌詞は嫌だと彼は言い、小学生でも書けそうな中身のない歌詞の方がひどいとわたしは言い返す。 悩んでも仕方ないことなら悩むだけ無駄だと彼は言い、悩みながらでないと前に進めない人もいる、とわたしは主張する。
それでも楽しさはあった。 自分と一八〇度異なる彼の考え方や価値観は、多分に新鮮でもあり刺激的でもあった。 ただし、ひとたび意見の食い違いが問題となって表面化すると、これっぽっちも共感できない二人は歩み寄ることすらままならず、その度にお互いに疲れ果て、あきらめのうちにうやむやにするしかなかった。

一年が過ぎ、このままでは二人のためにならないと考えたわたしは、ある一大決心をする。広紀が一人で住んでいたマンションに転がり込み、同棲を始めたのだ。 生活を共にすることにより二人の価値観をなじませていきたいという、消極的なわたしにとって蛮勇ともいうべき覚悟をもって臨んだことだった。
ところが今度は価値観どころか、日々の暮らしの些細な差異でさえ、二人の間に溝を生んでしまう。 バスタオルなんて二輓使ってから洗えばいいと彼は言い、その都度洗わないなんてありえないとわたしは答える。 夜は部屋を真っ暗にしないと眠れないと彼は言い、明かりがないと不安でたまらないとわたしは言い返す。 二人で過ごす今が楽しければ他には何もいらないと彼は言い、二人で過ごす将来のために今を厳しく律していきたいと、私は主張する。

この二年間、我ながら本当によくもったものだと思う。 ではなぜ、不一致をひしひしと感じながらも、これまで別れを選ばなかったのか。
単純なことだ。やっぱりわたしは、広紀のことが好きだった。 気持ちだけでは、どうしようもないこともあるのだ。
新幹線の車内アナウンスが博多南駅に着いたことを告げたとき、わたしは泣いていた。 すべての乗客が降りていく。 わたしの横を通り過ぎる誰かが、興味ありげにこちらをうかがっているのを感じる。
けれどもわたしは、立ち上がることができずにいた。
「行こう、清子ちゃん」
広紀がわたしの腕をつかんで引っ張り上げる。 しゃくりながらもわたしは、片手に旅行カバンを提げてホームに降り立つ。
同乗者たちはすでに去った後で、駅はしんとしていた。
こんな賭け、やる前から結果は見えていた。 それでもわたしは、確かめてみたかったのだ。

二人の旅の終着駅に、彼が何を望んでいるかをーーー。 こんな馬鹿げた賭けに広紀が、みずから幕を下ろすのか否かを。 改札を出ると、彼はわたしのまぶたをこする手を取った。 そして優しく握り、私の半歩先を行く。
ーーー客室には、誰も入ってこなかった。 この結果を受け入れるのが、よいことなのかどうかはわからない。 わたしはどうせ、一緒にいればいるだけケンカをし、その度に疲れてしまうだろう。
でも今は、きっと大丈夫だと信じたい。 気が合わないことばかりだけど、二人にとってもっと肝心な部分で、わたしと広紀の思いは一致していたのだから。 気持ちだけではどうしようもできないこともある。 でも、気持ちがなければ、どうにかしようと思うことさえないはずなのだ。
二泊三日の京都旅行最終日の夕刻、二人の暮らす那珂川町現人橋のマンションに向けて、陽射しの残る道に足を踏み出すとき、私はこみ上げるなみだをこらえ、半歩先の広紀に言ってのけた。
「それじゃ、これからも恋人ってことでよろしく。広紀くん」
JR博多南線、博多駅から博多南駅まで新幹線でひと駅、片道二九〇円。 およそ九分間におよぶ賭けを乗り越えた、二人の旅の終着だった。
一覧に戻る

「博多南駅」
脇山博司
「ーーーじゃあさ、賭けをしようよ」
二泊三日京都旅行最終日の夕刻、乗り込んだ博多南行きの新幹線が動き出すと、わたしは隣の席で居心地悪そうに携帯電話をいじる恋人の広紀にそう告げた。散々な旅行だった。
何もかも任せると言いきった広紀に代わってわたしが、博多駅を発つ頃から綿密に組み立てたプランを、彼はことごとく無視して気ままに振る舞った。
初日、三十三間堂で自分と似た顔の千手観音を探し始めた彼に付き合って、銀閣寺の閉門に間に合わず。二日目の嵐山では、渡月橋からいきなり桂川の上流を目指してずんずん歩き出した。彼を追ったせいで、龍安寺の高名な石庭を拝めずじまいとなってしまった。
とうとう昨晩、食事の途中でケンカになった。

予定を狂わせたことを責めると広紀は、
「いいじゃんか。清子だって、俺にそっくりな像を見つけたときも、上流の方でもっときれいな紅葉を見られた時も、すっげぇはしゃいでたくせに」
開き直るのも腹がたつし、彼の言うとおりなのはいっそう腹が立つのだ。
結局わたし達は仲違いしたまま、最終日の今日は、すでに指定席を抑えてあった帰りの新幹線に乗るまで、完全に別行動となった。
合流しても二人の溝は埋まらず、しびれを切らしたわたしはついに、持ちかけたのだ。
ーーー賭けをしよう、と。
「賭けって、どんな」
心当たりがないはずもないのに、広紀は怯えるように頭を上げて問いただす。
「わたしたちが新幹線を降りるまでに、この客席に入ってくる人が一人でもいたら、わたし達は別れる。誰も入ってこなければ、別れない。それでどう」

百パーセントとまでは言わない。 が、こんな賭け、やるまでもなく結果は見え透いていた。それこそ終着駅を目指す新幹線のような、行き着く先の判りきった賭け。
それでもわたしは、確かめたかったのだ。 二人の旅の終着に、彼が何を望んでいるのかを。 広紀は少したじろいて、しかし深く悩むこともなく、答えた。
「いいよ」
新幹線が加速する。 わたしは背もたれに頭をあずけ、客室の前方に設けられた自動ドアを、祈るような思いで見つめた。
「じゃあさ、賭けをしようよ」
あれは二年前。 ひょんなことで知り合ってからというもの、しつこく誘ってくる広紀に根負けして、初めて二人で会った日の帰りのことであった。
彼と過ごした時間は楽しかった。 彼のことを、少なからず魅力的だとも思った。 しかしその一方でわたしは、この人とはとことん気が合わないな、とも感じていた。
何しろ彼は社交的で行動派、対するわたしは引っ込み思案。 アウトドアでスポーツを好む彼と、屋内で読書を愛するわたしとではとうてい、相性がいいとは思えない。

恋愛だって、どういうわけかこんなわたしにも積極的にアプローチしてくれる彼に対し、わたしはしぶりにしぶってようやく、デートぐらいならという気になった。
なのに彼はもう、付き合ってくれなどと言い出すのだ。 どちらかと言えば、断る方に傾いていた。
せめてもう少し様子を見たかった。 けれどもはっきり答えを出せずにいるわたしに、広紀が告げたのが先の台詞。
「俺は大橋駅で降りるから、それまでにこの車両に入ってくる人が一人でもいたら、俺と付き合ってよ。誰も入ってこなければ、今日のところは潔くあきらめる」
「意味わかんない。どうしてそんなことで決められなくちゃいけないの」
「清子ちゃんが自分で決められないなら、他の人に決めてもらうしかないだろ」
憮然としつつもわたしは考える。 二人を乗せた電車はそのとき、高宮駅に停車していて、ちょうどホームに面した扉が閉まったところだった。 次の大橋駅まではたったの二分、隣の車両から乗客が移ってくる可能性はゼロではないが、きわめて低いと思われる。
つまり、ここはひとまずあきらめてもらうことができ、彼との交際については結論を急がずに済む。

「いいよ」
わたしはうなずいた。
同時に電車が高宮駅のホームを離れ、大橋駅へと向かう、そう混み合ってもいない車内に人の動きはほとんど見られず、程なく電車は減速し、わたしが賭けに勝ったことを確信し始めたときだった。
広紀が突然、わたしのそばを離れて歩き出したのだ。 初め、降車に備え、乗車口の前まで移動しているのかと思った。 ところが彼はそこで立ち止まらず、なおも歩みを進める。
その先にあるものを見てわたしは、嫌な予感に顔をしかめた。 予感は的中した。 広紀はいったん隣の車両に移ると、すぐさまきびすを返し、また元の車両へ入ってきた。 そして、わたしに言ってのけたのだ。
「それじゃ、今日から恋人ってことでよろしく。清子ちゃん」
折しも電車は大橋駅に到着し、開いた扉から広紀は出ていった。 あまりにも馬鹿馬鹿しい決着にわたしは、電車が動き出したのちも固まってきり動けず、気がついたら自宅の最寄り駅雑餉隈駅を三つも通過していた。

「ーーー呆れてものも言えないってのは、まさにああいう心境をさすんだろうね」
新幹線が出発してから、五分が経過しようとしていた。
わたしが非難めかしく言うと、広紀は肩をすくめる。
「いいじゃんか。断ろうと思えば断れたはずだろ、そんなズルはなしだって」
「だね。あのときは何だか、もういいやって気分になっちゃった」
賭けの結果を受け入れたことが、よかったのかどうかはわからない。 けれどもわたしは、その判断を悔いたことはない。 まして人のせいにするつもりはない。

ふぅ、と息を吐き出すと、わたしはあまり間を置かずに続ける。
「いいんだよ、こんな賭け、さっさと終わらせてしまっても。そんなズルはなしだって、そんなこと、わたしは絶対に言わないから」
広紀は何も答えなかった。 わたしは腕時計を一瞥し、再び、自動ドアに視線を戻す。
二人の賭けは、まだ終わらない。 付き合う前の懸念は正しかった。
らとにかく二人は気が合わないのだ。 休日くらい外へ行こうと彼は言い、休日くらい家で休ませてとわたしは答える。 何が伝えたいのかわからない自己陶酔みたいな歌詞は嫌だと彼は言い、小学生でも書けそうな中身のない歌詞の方がひどいとわたしは言い返す。 悩んでも仕方ないことなら悩むだけ無駄だと彼は言い、悩みながらでないと前に進めない人もいる、とわたしは主張する。
それでも楽しさはあった。 自分と一八〇度異なる彼の考え方や価値観は、多分に新鮮でもあり刺激的でもあった。 ただし、ひとたび意見の食い違いが問題となって表面化すると、これっぽっちも共感できない二人は歩み寄ることすらままならず、その度にお互いに疲れ果て、あきらめのうちにうやむやにするしかなかった。

一年が過ぎ、このままでは二人のためにならないと考えたわたしは、ある一大決心をする。広紀が一人で住んでいたマンションに転がり込み、同棲を始めたのだ。 生活を共にすることにより二人の価値観をなじませていきたいという、消極的なわたしにとって蛮勇ともいうべき覚悟をもって臨んだことだった。
ところが今度は価値観どころか、日々の暮らしの些細な差異でさえ、二人の間に溝を生んでしまう。 バスタオルなんて二輓使ってから洗えばいいと彼は言い、その都度洗わないなんてありえないとわたしは答える。 夜は部屋を真っ暗にしないと眠れないと彼は言い、明かりがないと不安でたまらないとわたしは言い返す。 二人で過ごす今が楽しければ他には何もいらないと彼は言い、二人で過ごす将来のために今を厳しく律していきたいと、私は主張する。

この二年間、我ながら本当によくもったものだと思う。 ではなぜ、不一致をひしひしと感じながらも、これまで別れを選ばなかったのか。
単純なことだ。やっぱりわたしは、広紀のことが好きだった。 気持ちだけでは、どうしようもないこともあるのだ。
新幹線の車内アナウンスが博多南駅に着いたことを告げたとき、わたしは泣いていた。 すべての乗客が降りていく。 わたしの横を通り過ぎる誰かが、興味ありげにこちらをうかがっているのを感じる。
けれどもわたしは、立ち上がることができずにいた。
「行こう、清子ちゃん」
広紀がわたしの腕をつかんで引っ張り上げる。 しゃくりながらもわたしは、片手に旅行カバンを提げてホームに降り立つ。
同乗者たちはすでに去った後で、駅はしんとしていた。
こんな賭け、やる前から結果は見えていた。 それでもわたしは、確かめてみたかったのだ。

二人の旅の終着駅に、彼が何を望んでいるかをーーー。 こんな馬鹿げた賭けに広紀が、みずから幕を下ろすのか否かを。 改札を出ると、彼はわたしのまぶたをこする手を取った。 そして優しく握り、私の半歩先を行く。
ーーー客室には、誰も入ってこなかった。 この結果を受け入れるのが、よいことなのかどうかはわからない。 わたしはどうせ、一緒にいればいるだけケンカをし、その度に疲れてしまうだろう。
でも今は、きっと大丈夫だと信じたい。 気が合わないことばかりだけど、二人にとってもっと肝心な部分で、わたしと広紀の思いは一致していたのだから。 気持ちだけではどうしようもできないこともある。 でも、気持ちがなければ、どうにかしようと思うことさえないはずなのだ。
二泊三日の京都旅行最終日の夕刻、二人の暮らす那珂川町現人橋のマンションに向けて、陽射しの残る道に足を踏み出すとき、私はこみ上げるなみだをこらえ、半歩先の広紀に言ってのけた。
「それじゃ、これからも恋人ってことでよろしく。広紀くん」
JR博多南線、博多駅から博多南駅まで新幹線でひと駅、片道二九〇円。 およそ九分間におよぶ賭けを乗り越えた、二人の旅の終着だった。